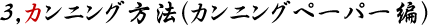

カンニングペーパーというのは、カンニング行為としてもかなり代表的な例であり、皆さんもご存知であると思う。
しかし、この方法はかなり上級レベルな方法でありますので、今までにカンニングを経験したことがない、初心者の方はお気をつけください。
まず、この方法の長所は、暗記系のテストであれば、かなりの確率で高得点が狙える。短所としては、物的証拠が残ってしまうことだ。
カンニングにおいて、このように紙切れで証拠が残ってしまうのは言い逃れできないのでかなり危険だ。(まぁカンニング自体が危険なのだが)
この方法はかなり気合いを入れてから行ってください。
まぁ最低、カンペを作るのに一時間ぐらいはかけてください。「一時間あればそれぐらい覚えられるよ。」という方は、覚えた方がよいでしょう。

まず、カンペと聞くと小さい紙に、小さい字で、細かく書いている紙。と想像してしまう方も多いと思うが、実際にはもっと簡単に作れるのだ。
ここでは、手書きの方法と、パソコンを使う方法の二つを紹介する。

|
1.普通のノートを用意する
2.一枚ちぎる
3.その片面に、ノート、教科書、参考書を見ながら、普段より少し小さい字で大事なところをまとめていく。(ノート片面に全て収まるようにかいてください)
注 : このとき、どの問題の答えがどこにあるかを、最低限暗記しててください。テスト中は一瞬が勝負ですので(笑) |
|
4.全て書き終えたら、お金を持って(まぁ50円ぐらい)近くのコンビニに向かってください。
5.コンビニにいくと必ず端の方にあるコピー機で、先ほどの紙を縮小コピーにかけます。大体、手のひらに収まるぐらいでよいでしょう。7cm×7cmぐらいの大きさでも十分に読めるはずです。
6.不要な部分をはさみ、カッターなどで切り取る。
7.カンペの完成です。見やすいように赤色などで、色分けしてもよいでしょう。カラーコピーもありますしね。

1.まず、パソコンを用意してメモ帳を開く。
2.ノート、教科書、参考書を見ながら、大事なところをまとめていく。
3. サイズ(7cm×7cmぐらい)を合わせて印刷。
注 : ホームページを作れる方は、いつもの要領で、色などを全て振り分け、見やすいように編集してから、サイズ-2ぐらいで印刷してもよいだろう。
4.不要な部分をはさみ、カッターなどで切り取る。
5.カンペの完成です。見やすいように赤色などで、色分けしてもよいでしょう。

いつも皆さんはカンペをどう使っているだろうか?
たとえば、机のなかに隠して持っていて、テスト中に出したり引っ込めたりしながら使う。これは、よくある手だ。
ポケットの中に隠していて、出したり引っ込めたりしながら使う。これはかなり使いにくいと思う。
でも、実際のテストで、机の中や、ポケットなどから出すのはかなり大きいアクションを必要とし、試験官に、「私は、カンニングをしますよ」と自分でバラしているのも同じだ。
カンペを見るのには出来るだけ少しの動きで、物音をたてない方が良いに決まっている。
では、いっそのこと机の上に出してしまってはどうだろうか?

この方法では、試験がはじまる前に、カンペの方に少し細工が必要となる。
コンビニ、またはスーパーで、両面テープを買ってくる。
カンペの裏の青い部分に両面テープを貼り付ける。これで、準備は完了だ。
注 : はく離紙は、まだはがさないこと。 |
|
学校で、テスト開始の前に、はく離紙を2枚ともはがし、粘着テープの方を上にして机の中に隠す。机とくっつかないように注意してください。
テストが始まる。
次のように、問題用紙と、解答用紙の2枚が配布された場合。(問題用紙はB4で片面のみとする。)
まず、問題用紙の方を、問題が見えるように半分に折る。
その後、図のようにおる。
(解答用紙は何もしなくて良い) |
|
試験官に注意しながら、すかさず、机の中のカンペを取り出し、図の部分に静かに貼り付ける。
このとき、きれいに張らないと問題用紙にしわが入ってしまうので注意が必要です。 |
|
さぁ、ここまで来たら、後は落ち着くだけだ。
試験官に十分注意し、図のように、親指で、上の紙を、パラリ、とめくればいいのだ。このとき右手は、シャーペンを持ちながら書いているフリや、悩んでいるフリをしていればよい。
オーバーアクションは命取りなので気をつけてください。
試験官が自分の横などを通る場合は、また紙を、パラリ、と戻して手のひらをのせて置くと、そこにカンニングペーパーがあるなんて絶対に分からない。上から見ても簡単に見破れるほどは、透けていないだろう。
とりあえず、手で隠していれば大丈夫だ。
あなたは、カンペを見ながら確実に問題を解いていけるだろう。

この方法は、試験官に近い席などでは少し危険な方法です。自分の席の場所によってかなり危険度も変わってきます。右利き、左利きなども考えておく方が良いでしょう。
間違っても解答用紙のほうに貼らないでください。
テストが終わると、問題用紙は、すかさず自分のかばんへ入れてください。問題用紙回収の場合は、「ハラが痛くなった」と言って、トイレに駆け込んでうやむやにしてください。(どうせ、枚数など数えてません)
今回の方法では、両面テープを使用していますが、両面テープの意味は、風などで飛んでいないようにするためだ。万が一、問題プリント落としてしまっても、すぐに拾えばバレないだろう。
別になくてもいけます。それに、ないほうがいい場合もあります。
例 . 両面テープで貼ってしまうと、プリントの半分の面の問題が終わってしまうと、裏面が非常にしにくいです(笑)

この方法も両面テープを使います。まず、コンビニ、またはスーパーで、両面テープを買ってくる。
|
カンペの裏の青い部分に両面テープを貼り付ける。これで、準備は完了だ。
注 : はく離紙は、まだはがさないこと。 |
|
ここまでは、先ほどと同じです。
そして、学校に行く前、家で制服を着るときにカンペの、はく離紙をはがし、図の部分にピッタリと貼り付けます。
そして試験がはじまると、先ほどと同じように試験官に注意しながら、パラリ、パラリと見てください。
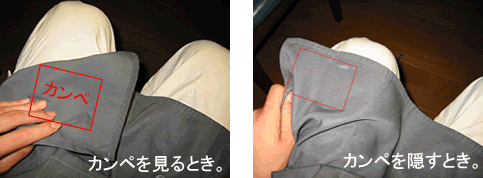
注 : このとき、めくった時に文字が自分の方に向くように貼ってください。
画像は、制服を着るのがめんどくさかったので、エプロンで撮影しました。
制服は、比較的、たけの長いものがお勧め。端が、太ももの上辺りにくるものが良い。(短すぎると無理です)
テストが終わると、すかさずトイレに行って取り外し、次の分をまた貼ればいいでしょう。

この方法も、また、両面テープを使います。まず、コンビニ、またはスーパーで、両面テープを買ってくる。
次に、ホームセンターなどで磁石を買ってくる。裏が全部磁石で、表には水性ペンでメモなどが残せるタイプのものが、安くてよい。(98円程)
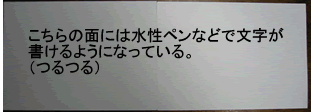 |
こちらが表面。
|
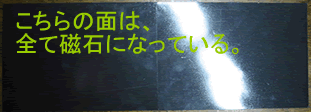 |
こちらが裏面。
(見えにくいので緑色にしました)
|
はさみ、カッターなどで半分に切って、マグネットの部分に先ほどのカンペの両面テープをはがして真ん中辺りに貼り付けます。
| 次に、カンペの裏の青い部分に両面テープを貼り付ける。
|
|
| そして、磁石の部分に両面テープで貼り付ける。
白い部分がカンペです。
これをテストが始まる前に机の下に貼り付けます。
注 : 鉄製の机でなければこの方法は使えません。
|
|
あとは試験中に、これを出してきて太ももの上辺りで読みます。試験官が来たら、また机の下に貼り付けておけばよいでしょう。
机の下を除かない限り絶対にバレないでしょう。
注 : 誤って落としてしまわないように注意してください。結構重いので音が鳴ります。 |
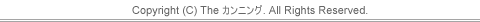
|